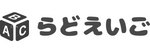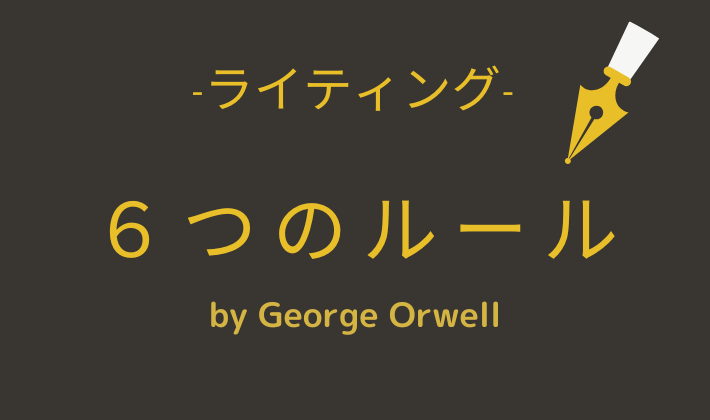「英語で読みやすい文章を書くのって苦手なんだよなあ...」
今回はそんな方に向けて "読み手にとって読みやすい英文を書くための6つのルール" についてご紹介していきます!
記事の内容
- 読みやすい英文を書く際の6つのルール
- 英文の読みやすさの確認方法
記事の信頼性

子育てをしながら社会人から、留学なしで英語を身に付けてきたプロセスをシェアしています。
この記事を読めば、ネイティブのような文章を書くための考え方を学ぶことができます。
英文添削講師をしている私ですが、その基礎となっているこちらのルールをぜひともマスターしていってください。
それでは詳しく見ていきましょう!
読みやすい英文を書く際の6つのルール

ではさっそく『読みやすい英文を書く際の6つのルール』について見ていきましょう。
このルールはイギリスの有名な作家であるジョージ・オーウェルが、一般人向けに紹介した『ライティング力改善のためのアドバイス』を引用しています。
ジョージ・オーウェルは日本人で言う所の夏目漱石レベルの知名度なので、情報の信憑性は確かです。
6つのルール
- 印刷物でよく見かけるような隠喩や直喩、あるいはその他の比喩を使うべきではない
- 短い言葉で用が足りる時に、長い言葉を使うべきではない
- 言葉を削ることができるのなら、必ず削るべきだ
- 能動態を使える時に、受動態を使うべきではない
- 日常的な英語が思いつく場合、外国語や学術用語、専門用語などを使うべきではない
- あからさまに野蛮な文章を書くくらいなら、これらのルールを破ったほうがいい
ルール1
まずは1つ目のルールが『印刷物でよく見かけるような隠喩や直喩、あるいはその他の比喩を使うべきではない』というものです。
英語では『Never use a metaphor, simile, other figure of speech which you are used to seeing in print』と説明されています。
こちらのルールは "比喩表現を使うことによって、書く英文に新鮮さがなくなってしまうこと" を危惧して提唱されました。
決まったフレーズに毎回頼っていては、自分らしい文章が書けなくなってしまうので注意したいですね。
例
- America is a melting pot:アメリカは人種のるつぼである
- America has diversity.
ルール2
続いて2つ目のルールが『短い言葉で用が足りる時に、長い言葉を使うべきではない』というものです。
英語では『Never use a long word where a short one will do』と説明されています。
こちらのルールは "読み手にとって読みやすい英文を書くため" に提唱されました。
例
- utilize
- use
ルール3
続いて3つ目のルールが『言葉を削ることができるのなら、必ず削るべきだ』というものです。
英語では『If it is possible to cut a word out , always cut it out』と説明されています。
こちらもルール2と同様に、読み手にとっての読みやすさを考えて作られたルールです。
語数を稼ごうと長ったらしい表現を使っても、その中身は空っぽだということです。
例
- due to the fact that
- Because
ルール4
続いて4つ目のルールが『能動態を使える時に、受動態を使うべきではない』というものです。
英語では『Never use the passive where you can use the active』と説明されています。
受け身の形を使うより "能動態の [主語 動詞] の順番が一番自然である"という考えに基づいています。
例
- Colombia was defeated by Japan.
- Japan defeated Colombia.
ルール5
続いて5つ目のルールが『日常的な英語が思いつく場合、外国語や学術用語, 専門用語などを使うべきではない』というものです。
英語では『Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent.』と説明されています。
日本語でもレジュメなどのカタカナ用語を使う人はいますが、これらは言っていることを分かりづらくしているだけです。
周りが理解できる言葉を使って説明するほうが何倍も賢いですね。
例
- nom de plume
- Japan defeated Colombia.
ルール6
最後の6つ目のルールが『あからさまに野蛮な文章を書くくらいなら、これらのルールを破ったほうがいい』というものです。
英語では『Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous.』と説明されています。
これらはずっと昔に作られたルールなので、絶対ではないということですね。
リズムの問題で長い言葉が適している時や、受け身のほうが大きなインパクトを与えることができるという状況もたくさんあります!

言葉は常に進化しているので、時にはルールを破ることも大切です
英文の読みやすさの確認方法

続いては「自分の書いた英文が読みやすいものなのかどうか?」確認する方法をご紹介していきます。
その方法は、無料で英文の読みやすさを数値として判定してくれるサイト "Flesch Readability Test" を使うことです。
"数値が高ければ高いほど読みやすい文章" という設定になっています。
アメリカ政府や新聞社なども使用していると言われている方式であり、信用性は高いと言われています。
数値の理想値は [60~80] の間だということです。
試しに英検1級と英検3級の長文問題を実際に入力したところ、以下のような結果が得られました。
英検1級の長文は非常に読むのが難しいと測定結果からも分かりますね。
英検1級・3級の読みやすさレベル
- 英検1級 : 29.7
- 英検3級 : 69.8
まとめ

今回の記事では『読みやすい英文を書くための6つのルール』をご紹介していきました。
これらを意識してエッセイを書くことができれば、読み手にとって分かりやすい高評価が得られるような文章が書けるはずです。
ライティング:6つのルール
- 印刷物でよく見かけるような隠喩や直喩、あるいはその他の比喩を使うべきではない
- 短い言葉で用が足りる時に、長い言葉を使うべきではない
- 言葉を削ることができるのなら、必ず削るべきだ
- 能動態を使える時に、受動態を使うべきではない
- 日常的な英語が思いつく場合、外国語や学術用語、専門用語などを使うべきではない
- あからさまに野蛮な文章を書くくらいなら、これらのルールを破ったほうがいい